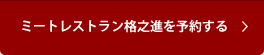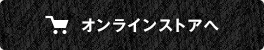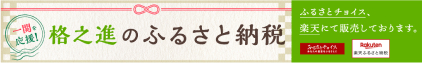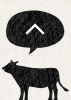【株式会社門崎 代表取締役】千葉 祐士×【ベイシー店主】菅原 正二
一関のジャズ喫茶「ベイシー」のマスターと熟成肉を語る
- カテゴリ
-

白い大きな蔵造の建物の扉を開けると、まるでビル・エヴァンスがそこにいるかのようなピアノの旋律が空気を震わせる中で、マスターはゆっくりと振り返り「おう、いらっしゃい」と迎え入れてくださいました。
ここは一関のジャズ喫茶「ベイシー」。
迎え入れてくださったマスター・菅原正二さんは一関小学校、一関中学校、一関一高を卒業した生粋の一関の人物。
若い頃からジャズに心酔し、早稲田大学在学中はビッグバンド「ハイソサエティ・オーケストラ」でバンドマス
ター・ドラマーとして活躍。卒業後も東京でプロプレイヤーとして演奏を続けていましたが、その後地元に戻り、自宅にあった蔵を改築しジャズ喫茶「ベイシー」を開店。マスターがかけるレコードを聴くために、全国津々浦々からお客様が集まります。

渡辺貞夫氏、坂田明氏、日野皓正氏、山下洋輔氏らの日本ジャズ界のスターたちの憩いの場であり、大学時代からの盟友・タモリさんもお店の常連で、番組『ヨルタモリ』内では菅原マスターを模した「ヨシワラさん」なるキャラクターを演じています。「伝説のジャズ喫茶」「ジャズ・オーディオの聖地」としてファンを魅了し、一関にまで呼び寄せてしまう伝説のジャズ喫茶「ベイシー」を司る菅原正二マスターは、格之進代表・千葉の憧れの人物です。
「伝説のジャズ喫茶誕生の裏側」
千葉:マスターはジャズドラマーとして東京でも活躍なさっていたのに、何がきっかけで一関に戻って、地元でやっていこうと考えたのですか?
菅原:ひとつ単純な理由があってね。おれ19歳の頃、大学浪人中に肺結核になっちゃって片肺切ってるんですよ。
長生きもできないだろうと思いながら、早大ハイソのあとプロになって赤坂のキャバレーで働いてたんです。
でも、60年代の東京って空気が悪かったんですよ。深呼吸しようと思って外に出たら、外の方がもっと空気が
悪かった(笑)。それで、地元に帰ってきてまた療養所に入ったんです。その時に、「ああ、おれこのままもう一回東京に行ったら、死んでしまうな」って思った。それで、こっちでなんかショボショボやってこうかな、と考えたわけです。そしたら、得意技って言うとおれはレコードしかないじゃないですか。レコードは蓄音機の頃から聴いてましたからね。公民館でレコード・コンサートを開いてお客さんに聴かせてたこともあるんですよ。

千葉:ええ!おいくつ位のときだったんですか?
菅原:高校生の時分かな、地域の人で満席になりましたよ。昔から、人にレコード聴かすの好きだったんでね(笑)。それから一関一高には古藤先生って戦前の芸大を出た一関にはもったいないくらいの偉い音楽の先生がいてね、ジャズにも理解があったわけ。その先生が音楽の授業で生徒つれてぞろぞろおれの家まできてレコード大会なんかやってたんですよ。当時わりと広いオーディオルームで「ステレオ」やってましたから。
(マスター、おもむろに立ち上がり颯爽とターンテーブルへ。レコードを換え、再び着席。)
千葉:じゃあ、高校生のときから人にジャズを聴かせてたわけですね。
菅原:もうね、一人で聞いてるってよりは、すぐに誰か呼びつけちゃうんですよ。分かち合いたい気持ちがあるんだろうな。まあ、いろんなレコードの聴き方があると思うんだけど、「聴かせ方」っていうのにも才能があると思いますよ。というのも、おれはもともと演奏する側だったでしょ。だから、自分が演ってるつもりでレコードかけるんです。受身で聴いてるんじゃなくって、「おれがレコード演奏して、みんなに聴かしてる」ってな感じでやってるんでね。だから響いてくる音が違うように感じると、スピーカーに向かって「そこは違うだろ!」なんて怒っちゃったりしてさ(笑)。よく公言してるんだけど、おれは「バンドリーダータイプ」の「レコード・プレーヤー」でね、なるべく演奏した人の音を正確に再現するように心がけてるわけ。レコードってのは面白くて、演奏した人がいて、録音した人がいて、プレスした音楽会社があって…いわば大量生産された工業製品の中に、意外や意外、ものすごいものが隠れてたってのが後になってわかってくるわけですよ。まだ世の中の人って気付いてないんだけど、レコードって原始的なギザギザの溝をエジソンが発明してから何も変わってない正体不明のもので、これは「魔物」。そのうち文化遺産になると思うよ。
(マスター、すっと立ち上がり、レコードを取り替える)
「気配の中に音がある」
千葉:(マスターの著書、『聴く鏡』を取り出し)マスターのご著書、愛読しているんですけど、「音の中に気配があるのではなく、気配の中に音があるのだ」、ここの部分で非常に共鳴するところがあるんです。わたしの得意分野だと、お肉の味っていうのは、生まれてから屠畜され、熟成をかけられて調理されて…という過程を経て目の前に饗されるんです。もっといえば、育てる人がいた、品種改良されてきた牛の先祖代々の流れがあった…と考えていくと、もう単純な美味しい美味しくないの世界ではなくなってしまうんですね。「この味の裏側はなんだろう」とか、「このお肉の個性、表情を最大に生かすにはどんな方法を試せばいいだろう」なんて考えながら…
菅原:社長はやっぱり肉の変態だね(笑)。でも、おれも本に書いているとおり、レコードに吹き込まれてるのは単なる音じゃなくて、録音されたその場の気配だと思ってる。だから、レコードを聴いてるの時に考えるのは「この演奏をしているとき、演奏家は何を考えてたのかな」「喧嘩してるのかな、仲良かったのかな」とか、まるでミステリー小説でも読むように、演奏している風景や正体を想像して読み解きたいんだよね。社長はそれを肉でやってるってのが、見ててわかりますよ。

千葉:そうしたところも含めて、マスターはわたしのお手本なんです。でも、「ベイシー」に絶対に届かない点というのがありまして、わたしたちは東京に出店してやっと一関にお客様をご案内できるようになったのですが、マスターはこの街を出ずに、圧倒的な音と魅力で全国からお客様を呼び寄せてしまうんです。
菅原:おれは一人しかいないからね(笑)。東京で支店をやらないか、とか話はいっぱいあったけど、おれが演奏してるから「ベイシー」がある。ここでおれが必死になってやってるからみんな来てくれるんで、おれが直にレコードかけてるから意味があるんですよ。それはプレイヤーの楽器と一緒でね。(パブロ・)カザルスがいなくなった時にチェロが残ってたって、・・・・。おんなじ話ですよ。・・天才バカボン。
「自分のやりたいことを、純粋にやる」
千葉:マスターはこれから一関がどんな風になっていったらいいと思いますか?
菅原:その件に関してはね、おれあんまりいろんな所に顔出さないじゃないですか。なんでかっていうとね、それぞれ個人が各分野に点在すればいいと思ってるんですよ。ラーメン屋ならうまいラーメンを40年間作ったら、お客さんたくさん来るでしょ。おれが「ベイシー」でやってることはそれと大差ないんだな。会議開いていいもの生まれた試しないですよ(笑)。会議開くと結局「観光客誘致」ってことに行きつくんだけど、それはちょっと違うんじゃないかなと思っててね。会議やると、「一関ジャズの町」みたいなことを誰かが絶対言い出すんだけど、そりゃインチキだよね(笑)。そういうのに顔出さず徹頭徹尾一人で黙ってやってると、誰かが覗き見に来るんですよ。だから、「音なら『ベイシー』、お肉なら『格之進』」って言う風に個人プレーを徹底していけばいいんじゃないかと思うんだな。

千葉:おっしゃるとおりですね。いくら観光誘致って言って表面を整えても、中身が伴っていることが大切ですからね。「また行きたい」「またあれを食べたい」「またあの人に会いたい」と思うようなものがないと…。
菅原:そうです、純粋な気持ちでやらなきゃいけないんですよ。会議開いて、やれゆるキャラだ、町興しだって、どこの町でもおんなじレベルのこと考えてるんですよ。おれそういうことにあんまり興味なくってね。インチキはだめですよ。観光客を呼ぶことが目的じゃなくって、自分の仕事を一生懸命やること、それが一番の根っこじゃなきゃだめじゃないかと思うんだね。自分がやりたいことを純粋にやりぬく、先輩(島地勝彦氏)がいうように「寛容な精神を持つ」こと。他人のことを否定したり、気を取られすぎず、個人のやれることをしっかりと続ければ、それでいいんじゃない?
そういって、マスターはまたレコードを換えに立ち上がりました。
一関の白い蔵では、今日も黒い円盤が回転し、スピーカーが再現する異空間で、風流なマスターと粋なお客たちが、ジャズに淫していることでしょう。




 ハンバーグ
ハンバーグ メンチカツ
メンチカツ
 塊焼き・塊肉(部位別指定購入可)
塊焼き・塊肉(部位別指定購入可) ステーキ・骨付き肉
ステーキ・骨付き肉 焼肉
焼肉 すき焼き・しゃぶしゃぶ
すき焼き・しゃぶしゃぶ 白金豚
白金豚 その他
その他